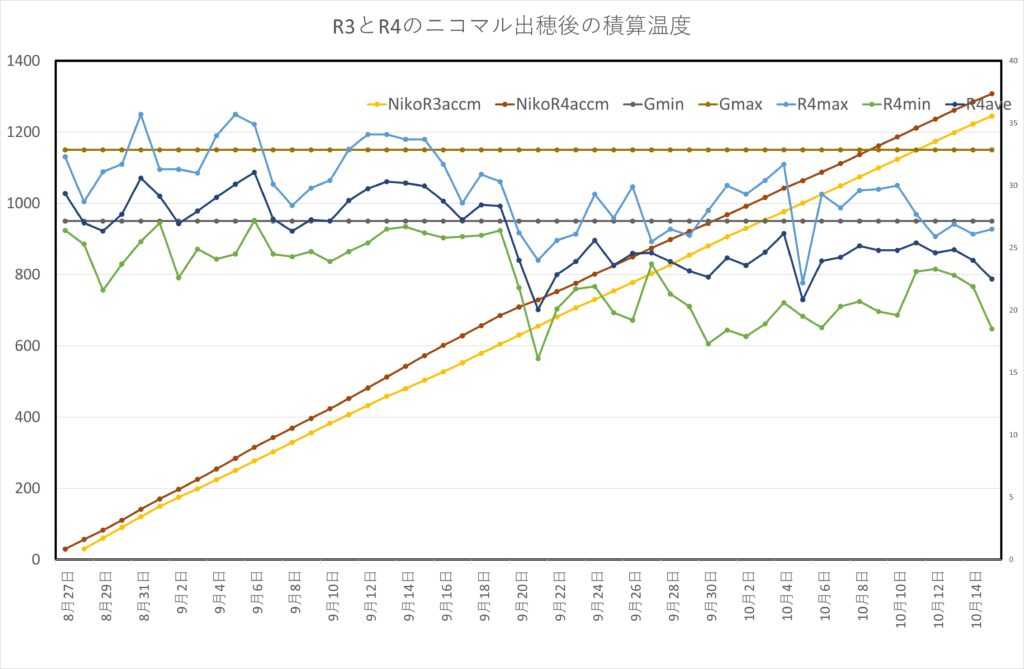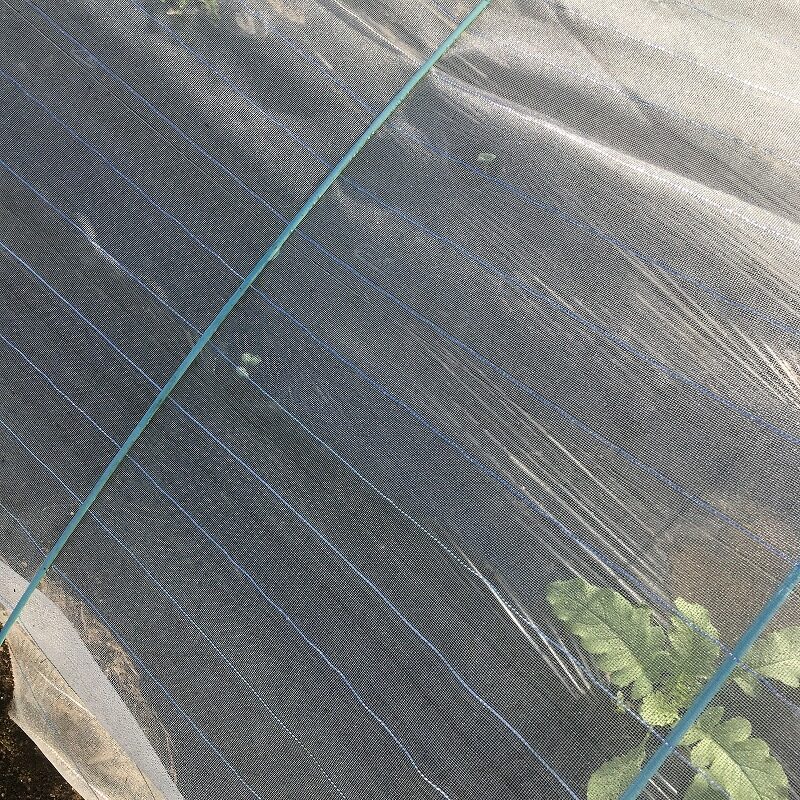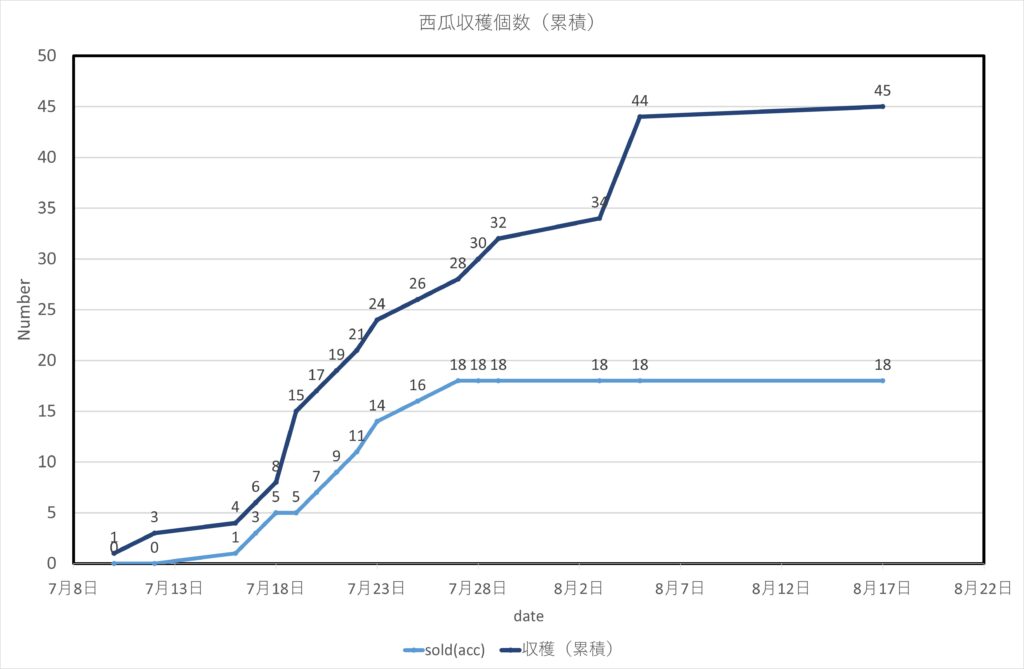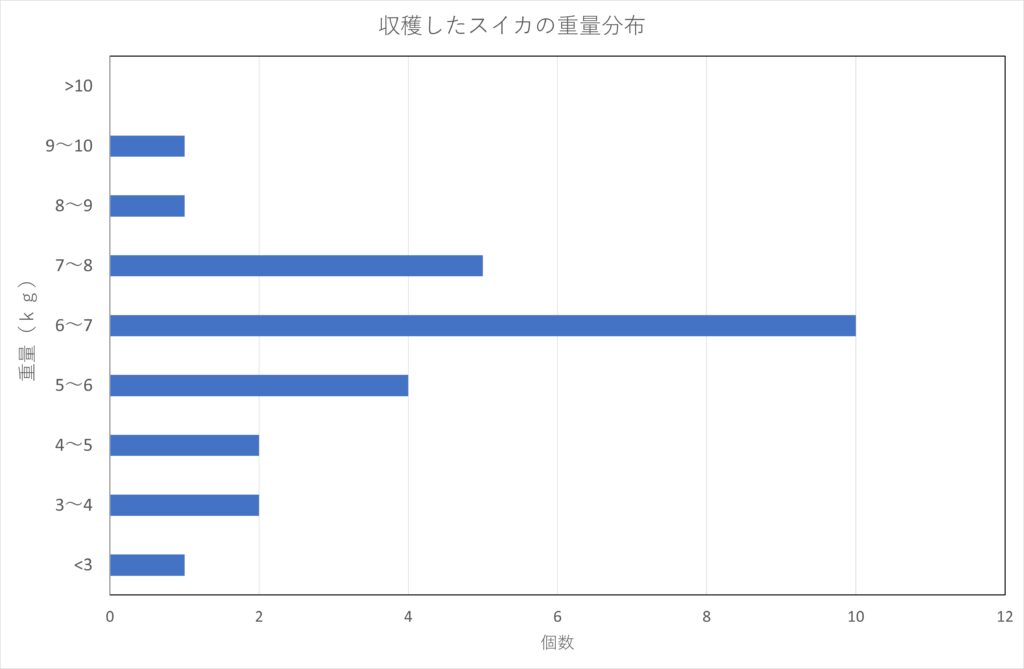2022年8月13日
から Mat Grimm
3件のコメント
2019年から野菜を作り始めて、4年目となり、年間の栽培サイクルが頭に入って、不十分ではあるが種まき時期や畑の準備を見通せるようになっている。しかし、あまり記憶に頼ると失敗することもあったので、注意が必要である。秋冬野菜はアブラナ科(ダイコン、白菜、カブ、ブロッコリー、キャベツ、芽キャベツ、ロマネスコ、ケールなど)が中心で畑の栽培箇所(20m×3畝、10m1畝)を連作障害を考慮して第一に決める。ダイコンやブロッコリーは成長すると防虫ネットを押し上げて、隙間から虫が浸入するので、幅1.8mの防虫ネットにすべて替えようと思う。白菜は植替えに弱いので直播としてきたが、これまで発芽率が低く、欠株箇所に追加で種まきしていたが、結局、玉にならずに花が咲いてしまうことになった。今年は直播に加えてポットにも種まきして欠株にはポット苗を植えることにする。ブロッコリーは頂花蕾を取るタイプと「スティックセニョール」などの茎をとるタイプがあるが、頂花蕾だけでなく、脇芽にも大きな蕾をつけるタイプ(セカンドドーム型)があり、1株で2個以上とれるのでこれを主としたい。カブはおいしいと言われる「金町こかぶ」を作ったが、虫に食われたり、発芽率が低かったりで意外に栽培が難しい。畑に長くおいても大きくならず、千枚漬けにもできないので、品種を変えて、作りやすい耐病タイプを作ろうと思う。次に玉ネギ、ニンニク、ラッキョウ、長ネギ等のネギ科で特に玉ネギは600個以上作り、今年は貯蔵性の良い小さくて固い玉ネギがとれた。極早生品種の「絹てまり」は遅く種まきしたにも関わらず、玉になるのも早く固いものができたがさすがに成長期間が短かったので玉が小さかった。今年はこの極早生を時期を逃さず種まきして、ある程度の大きさの新玉ネギとして産直に出したいと思う。貯蔵用としては中晩成の赤玉ネギが作り安く、固くて大きかったが用途が生食サラダ用に限定されているようで100個くらい作れば十分か。ほうれん草、ビーツ、フダン草(スイスチャード)などのヒユ科の野菜は発芽率が低く、まだコツを掴めていない。特にほうれん草はタイミング良く間引いて収穫しないと大きな葉の株は取れない。秋播きは赤い根まで食べられる日本種のほうれん草が向いており、「次郎丸」をつくる予定。問題は天候である。ビーツも3回くらい種まきして何とか欠株を埋めている状況である。気温と雨等を記録して、どのような時期に種まきすべきかを探りたいと思う。キク科のレタス、春菊は比較的作りやすい。玉レタスも春菊もタイミングを逃さず収穫しないと柔らかくておいしいものはいただけない。目につくところに植えることが意外と重要である。小松菜やフダン草、春菊、水菜などはハウスの中で作る方が虫の害も少なく、目につくので忘れなく収穫できる。
最近、炭素再生型農業という番組を見たが、これは有機農業とも異なり、土壌の中に炭素を固定する農業、多様な菌類や生物が土壌を豊かにし、その土壌を利用した農業ということらしい。トラクタによる耕耘、単一品種の栽培、化学肥料と農薬の投入というこれまでの工業的農業では土壌から炭素を収奪して、地球温暖化を加速するだけでなく、土地が痩せていく。不耕起の土地に家畜(牛や鶏など)を放し、草で土を覆うことで光合成で作物を通して土壌に炭素を供給し、微生物が生息することで作物に栄養を与えるという再生的な関係ができるという。私は不耕起栽培では栄養が足りず、作物は余り取れないと考えていたが、生物の生態系を崩さないということで不耕起にし、枯草や動物の糞尿などを投入することで生物が活発に土壌を豊かにすることで作物が育つらしい。無農薬で鶏糞等の有機肥料は投入してきたが、不耕起ではない。耕起して、土を細かく砕いて、上下を反転させ、空気の入ったサクサクの土を作り、それをマルチで覆うことで雨除け、雑草を防ぐことで作物の生育を保護している。どちらが地球にやさしいのかあるいは再生的なのか、大きな課題であると感じた。研究してみたいと思う。意外と農業はこれから、人類にとって重要な革新を必要とする分野ではないかと感じた。