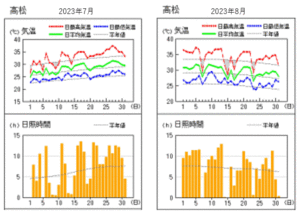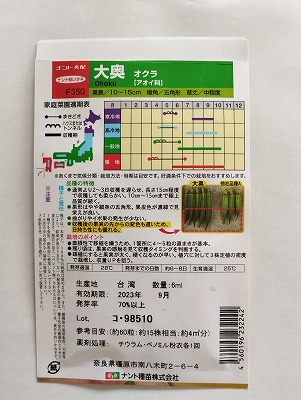夏の楽しみの一つは海水浴であるが、2,3年前から瀬戸内海に面した庵治半島にある小さな海水浴場に行っている。いつ行ってもビーチは混んでいない。半島には海沿いの細い道があってぐるっと周回できるようになっているが先端にももうひとつ海水浴場があるが、そこまでの途中にある、半島の真ん中あたりに高尻海水浴場がある。
瀬戸内海に面した小さな入江で砂浜も磯も突堤もあり、ゆっくりと海遊びができる。我が家から、車で30分位の距離で思い立ったら気軽に行けるのもよい。今年はお盆に近い12日に出かけ、少し海に浸かると、酷暑でゆるんだ身体の熱が取れるようで満足する。
砂浜にはいろんなものが漂着していて、歩きながら目を皿のようにして探す。貝がらや角の取れた色ガラスなども見つけると嬉しいが今年はなぜか、壁を塗るときに使う取っ手の付いた四角い板を見つけた。土を載せる面がプラスチックでできていてまだ使えるものである。使わないだろうと思いながら、もって帰ってしまう。
千葉の佐倉市に住んでいた頃は、海水浴というと外房の九十九里、御宿や内房の保田などへ行ったが遠いのでそれなりに準備が必要だった。
海だけでなく、山の涼しさも探検したくて探していたところ、近くに「虹の滝」というちいさな滝をネットで家族が見つけ、行ってみた。やはり、車で30分くらいの距離で県道であるが普通車だとすれ違いのできない道幅しかない道をくねくねと登り降りしながら行くと、道路に滝の場所を示す看板があり、そこで車を停め、道路から下の沢に降りていく。道路の谷側も木々が生い茂り、よく見ると川が流れているのが透けて見えるが、降りてみるとこんなに近くに滝があるなんて気づかなかった。
滝の高さは10-15mくらいではないだろうか。それでもかなりの水量が岩に沿って流れており、滝壷もちいさいながら、泳ぐこともできるくらいの広さである。しかし、さすがに山の水は冷たく、泳いでいる人はいない。ウエットスーツを着てボート遊びをしている。
驚いたのはその川のせせらぎの豊かさである。浅瀬と岩と砂のせせらぎには実にたくさんの生き物を見つけた。小石を除くと、沢蟹がいたり、ちいさな川魚もたくさんいる。あめんぼ、トンボ、蛙などいたるところに見つかる。そして、石菖という植物も岩にくっついて生えている。
子供の頃の近くの川ではこのようなところがあったが最近の農業用水路はコンクリート化、家庭用排水の富栄養化などでほとんど生物はいなくなっている。人新生という新たな地質世代に1950年代から入っているらしい。人の活動で急速に生物環境のバランスが崩れているらしいが、虫、植物がいなくなっても人間が生きていけるとは思えない。昆虫写真家であり、かつ里山の維持を提唱している今森光彦氏が「環境農家」を自称しているが、私も賛同する。「虹の滝」からもどり、捕まえた沢蟹と川魚を水槽に入れて、故郷のこの地域を生物多様な昔の里山に復活させたいと思うこの頃である。
- 高尻海水浴場
- プライベートビーチの様
- 虹の滝
- せせらぎの生き物