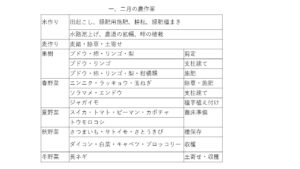県道に枝を伸ばしたセンダンの大木の伐採を某森林組合に依頼してあったが、いよいよ伐採となり、立ち会った。どうやって伐採するのか興味があったが、やはりバケット車の威力をまざまざと見せつけられた。センダンの木は道路から2m程度は隔たっていたが、道路から遠い方に伸びた枝も道路にバケット車を固定したまま、するするとほぼ真横に近い角度で人が乗るバケットが移動し、チェンソーで枝を切り落としていく。もちろん、道路側に伸びた枝はやや長めではあった(1.5mくらい)が、切り落とした直後に待ち構えた人がすばやく、片側通行で車が通る前にその落ちた枝を通行路線から素早く引き出している。片側通行の交通整理を三人が担当し、伐採はバケット車に一人乗り込んで、チェンソーで切り落とす人と下でそれを運ぶ人、積み上げる人の三人の伐採グループがいる。朝8時頃に現地に集合し、切り取った枝をどこに積み上げておくかを打合せして、まず県道沿いではなく、駐車場側にバケット車を固定して東側から伐採を開始した。その方が交通量が多い時間帯の道路使用を避けることができる。その後、9時頃には県道を片側通行にして、道路にバケット車を固定して、枝を外側から刈りこんでいく。1m程度の長さで切って枝を切り詰めていく。約1時間くらいでメインのセンダンの木の片側をほぼ短く刈りこんだ。そして、10時頃に小休止を取った頃、私は現場を離れて別の所にいたが、ランチ後に13:30頃に戻るとセンダンの木は短く根元で切られていた。そして、14:30には片付けを始め、周りを簡単に清掃して撤収している。太い幹は取扱いに困るだろうと持って帰ってくれた。見積もりでは伐採した木はそのまま畑に残すという条件であった。やはり、プロの伐採は無駄な動きがなく、効率的に伐採を進めていく。見事であった。
- 伐採前の高台
- 駐車場側に作業者を停めて伐採
- 駐車場側で伐採進む
- 周辺からチェンソーで切り取る
- センダンの道路側から切り詰める
- とにかく伸びるバケット
- 積み上げた枝と裸の高台
- 太い幹は持ち帰る
- すっきりした高台とその奥の松