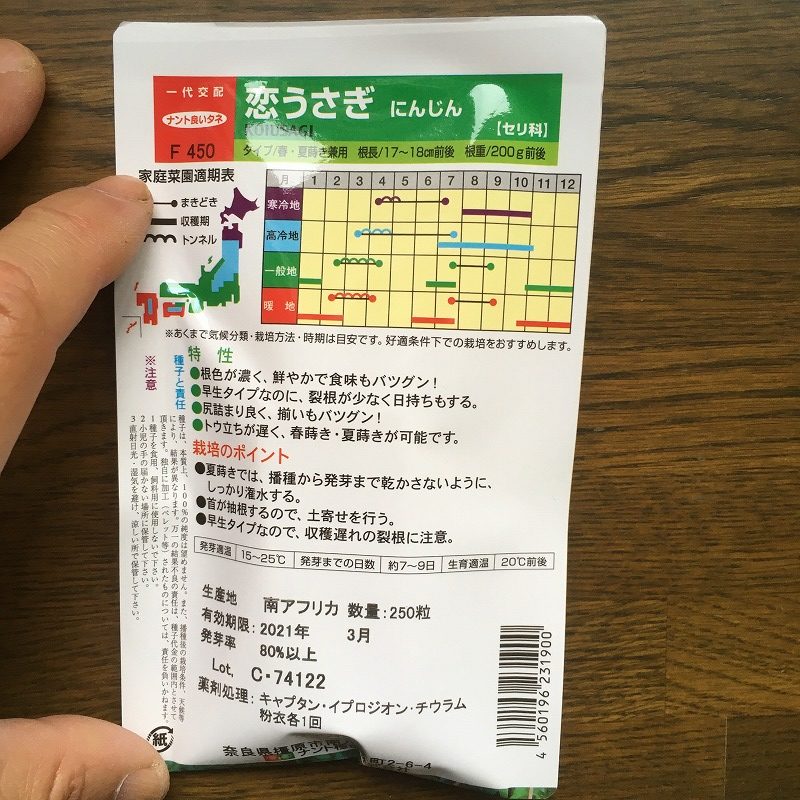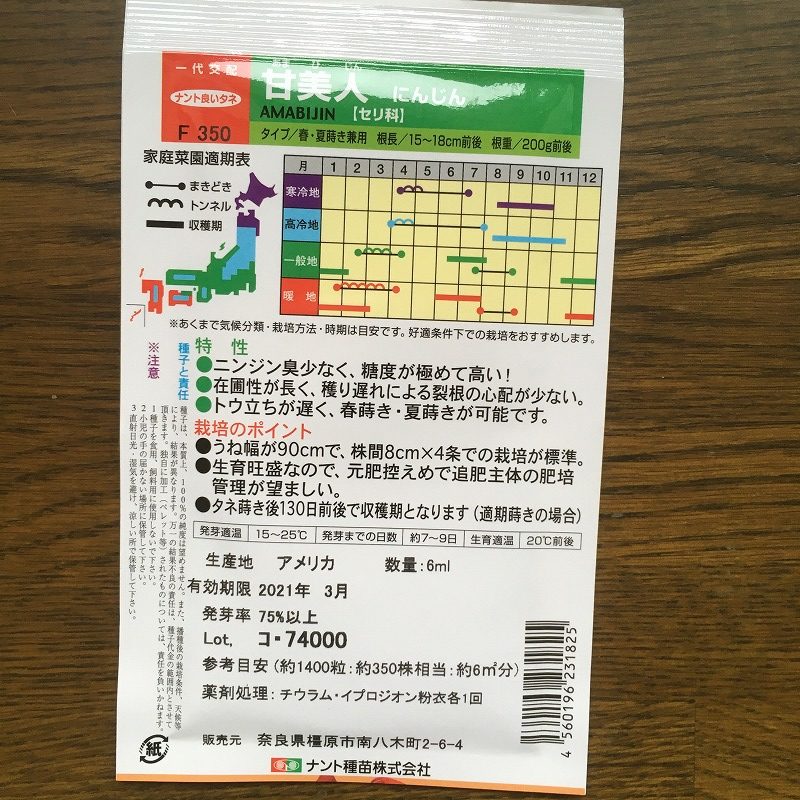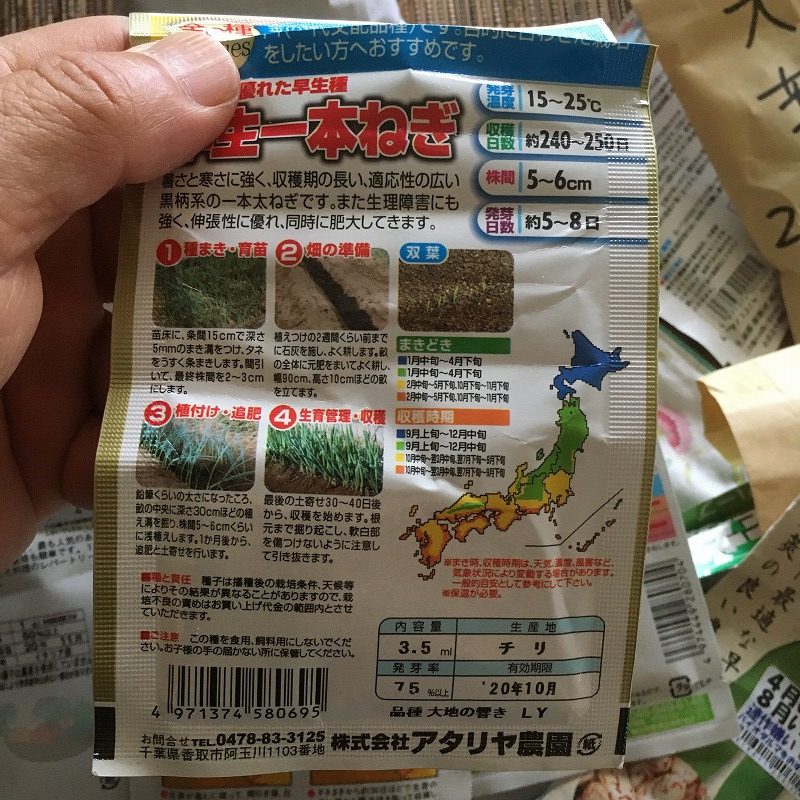今日は8月14日お盆の最中である。生憎、新型コロナウイルスの感染脅威のため、子供たちの里帰りもなく、夫婦ふたりだけの寂しいお盆を迎えている。お盆にはお供えと一緒に仏花が必須である。昨年は帰郷して間がなく、仏花を自前で育てることはできず、今年にその思いを持ち越していた。しかし、野菜やお米作りで忙しく、お花つくりまで余裕がなく、結局、お盆用の花は用意できなかった。単に畑の隅に花の種を播いただけでは育たなかった。雑草の勢いに負けていつの間にか雑草だけになっていた。
仏花としてどのような花が売られているか、産直に行って観察した。菊、ユリ、ハスの花、鶏頭、紺菊(アスター)などなじみの花に加え、カーネーションやトルコ桔梗などが人気のようである。昔、必ず添えられた千日紅は見られない。
その中でも紺菊は子供の頃からなじみのある花であり、種を播いて育てようとしたが思いのほか難しく、いまだに仏花としてふさわしい外観は得られていない。