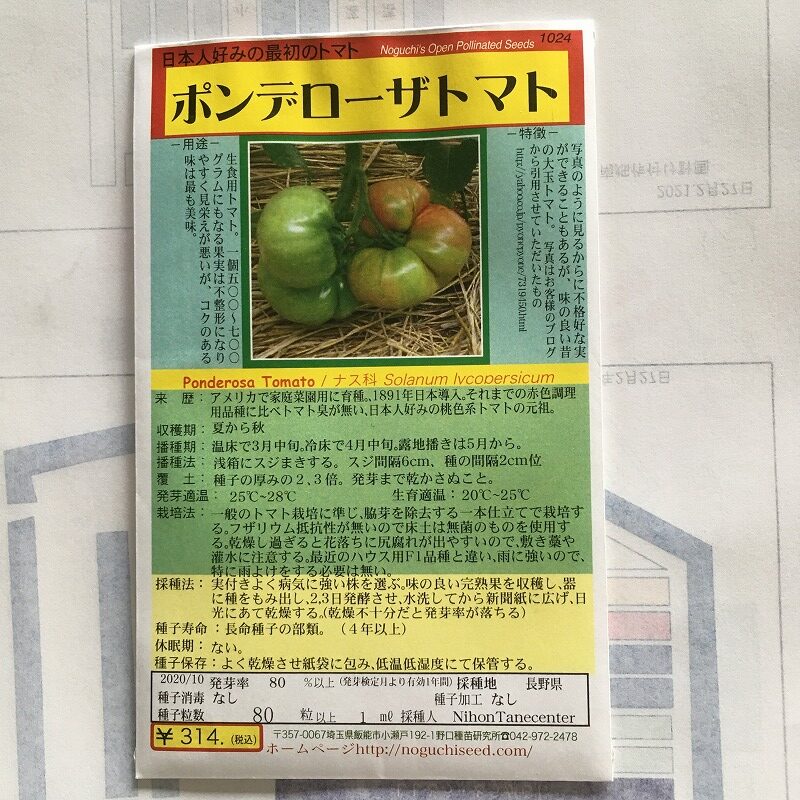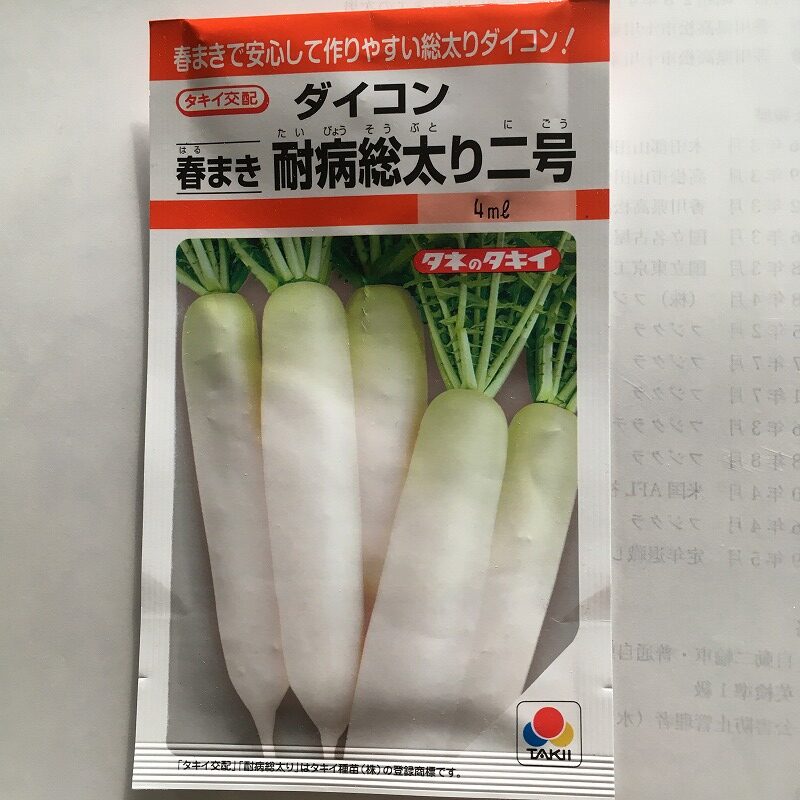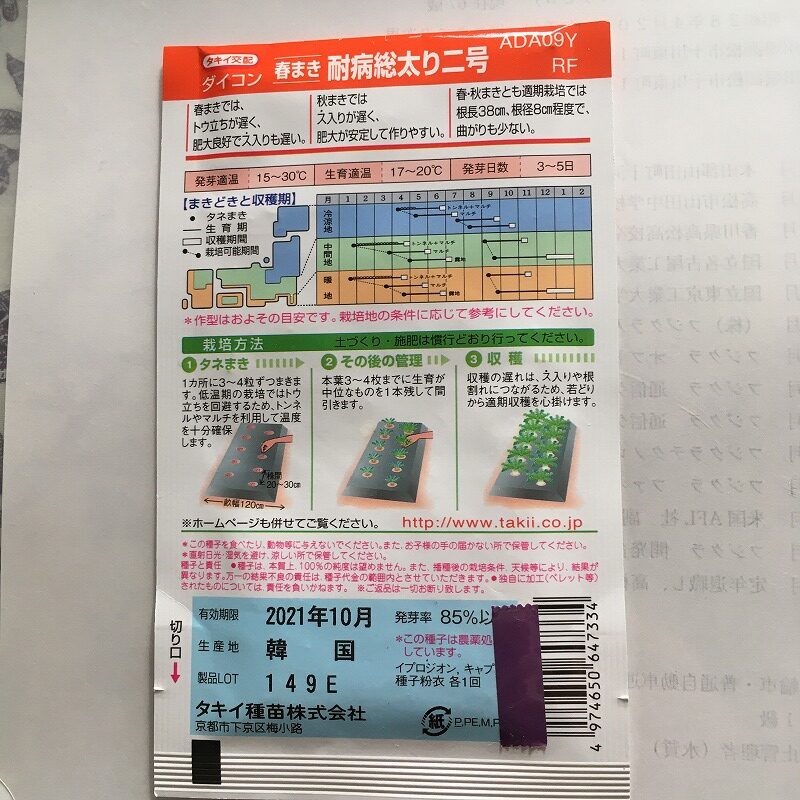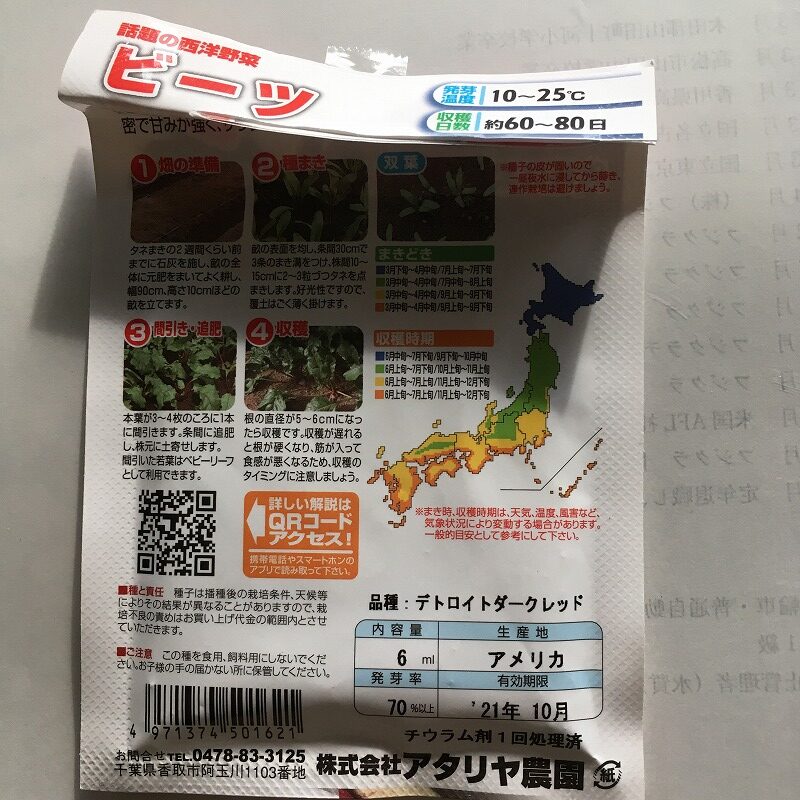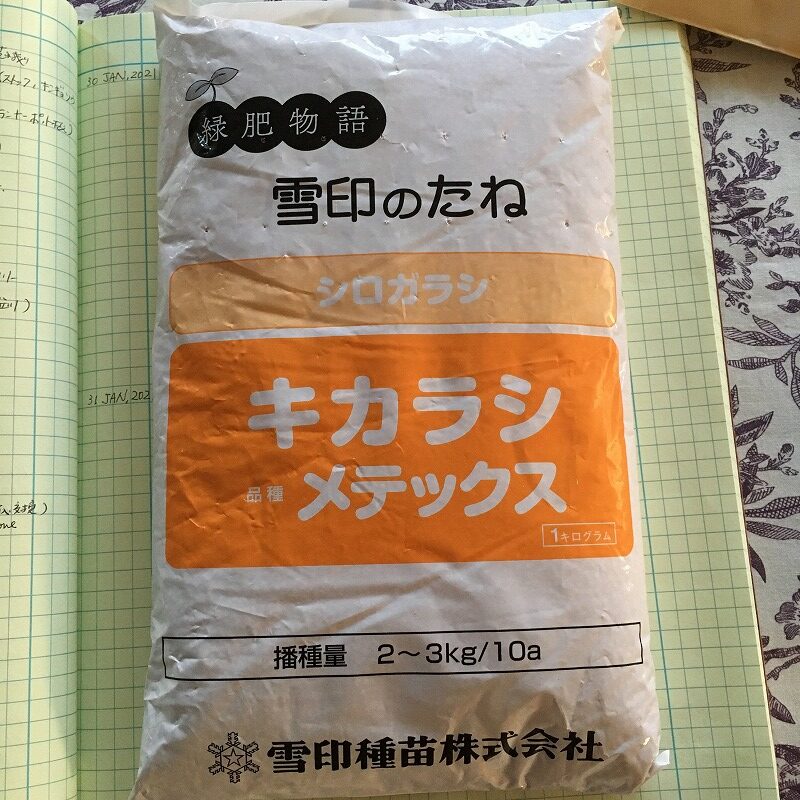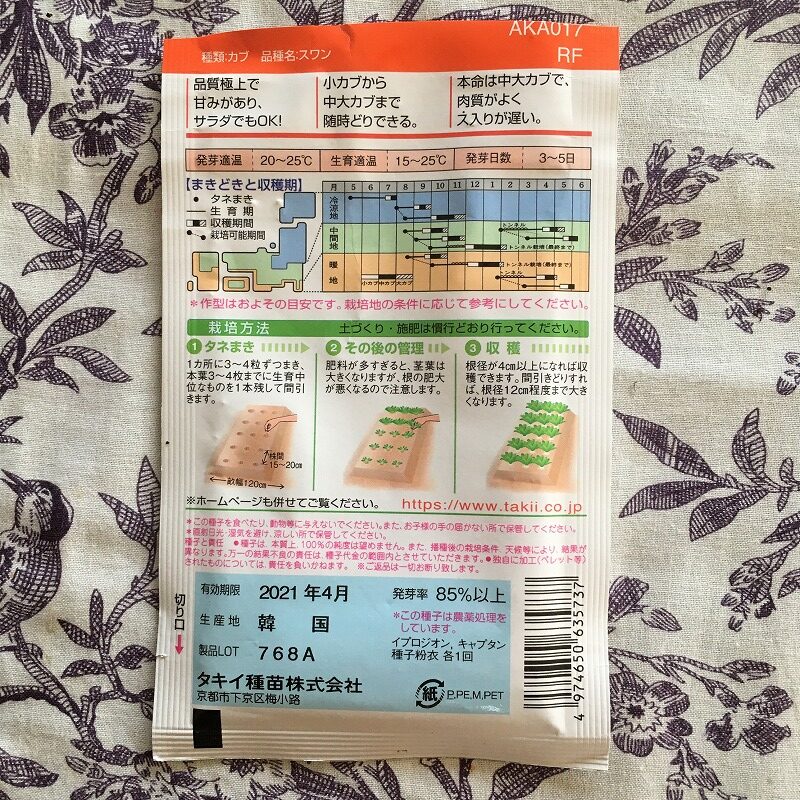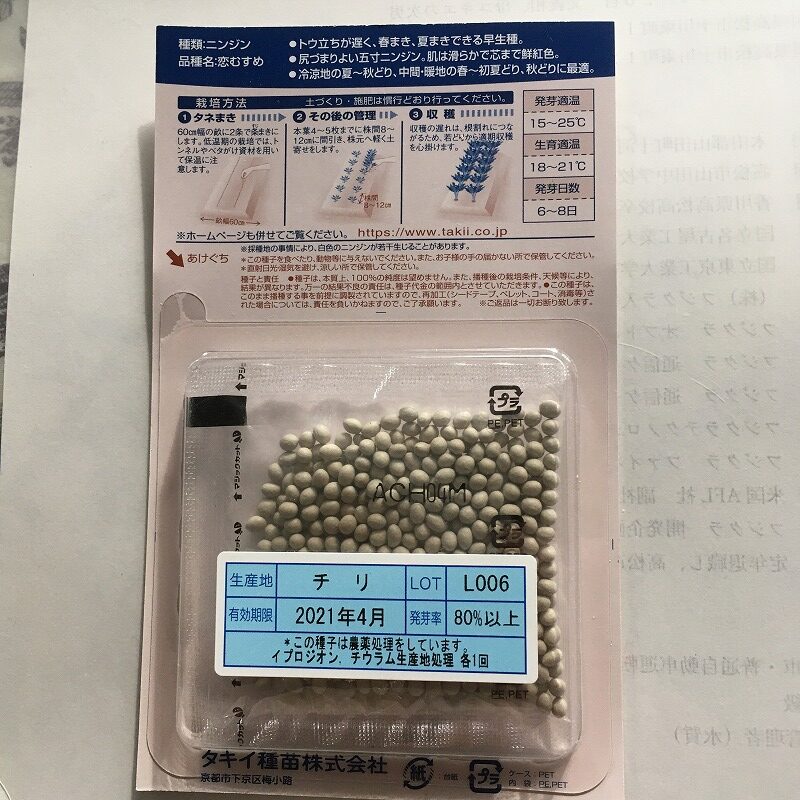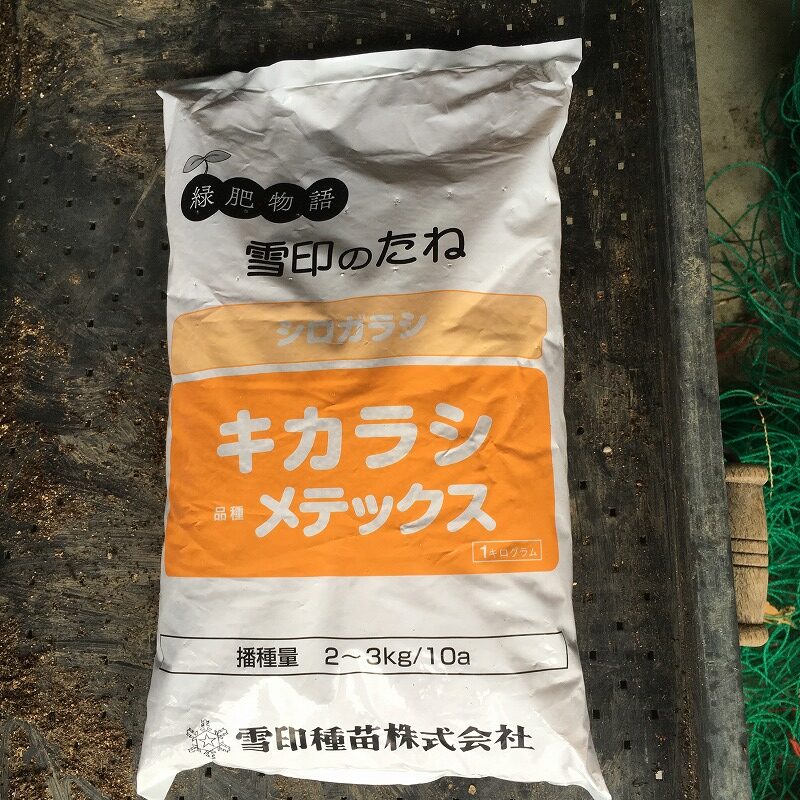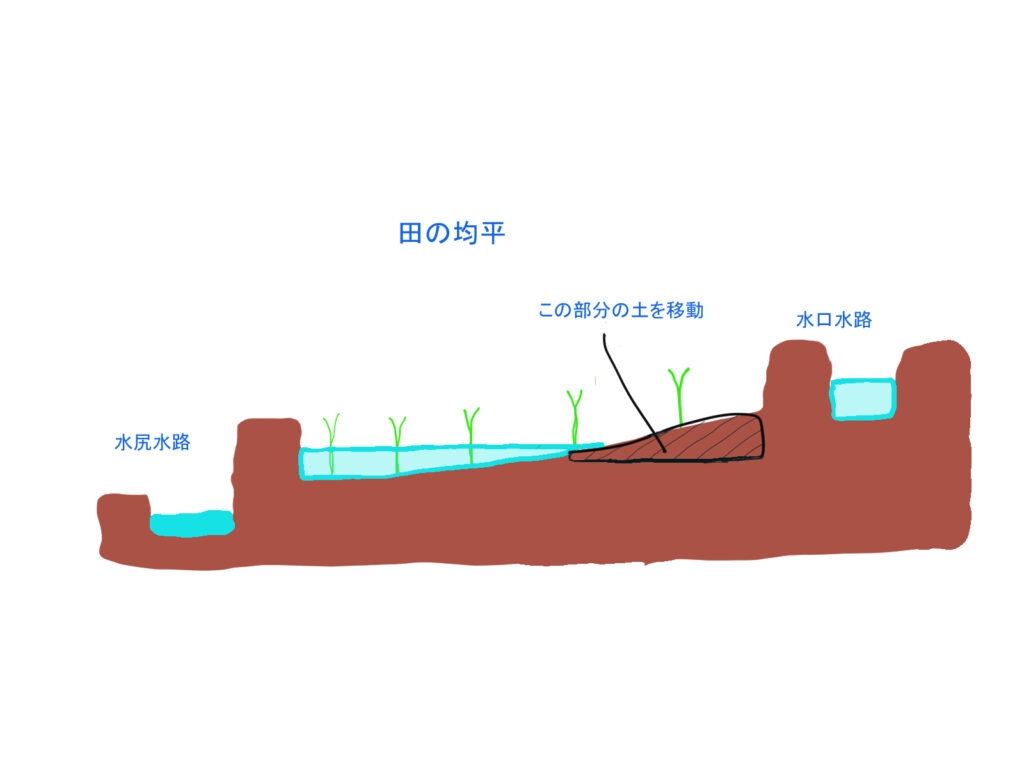子供の頃から動物を飼育することが好きであったが、サラリーマン時代は時間に制約があり、十分なケアを動物に注げないので自制していた。退職した今では時間も十分にある。だから、何でも飼えるのだが、子供時代とは異なり、慎重に考えて後悔のないようにしたい。ペットを中途で捨てることはできないし、何よりも旅行など長期の外出の制約になってしまうのが困る。
現在、猫を一匹飼っているが2019年に19歳3ケ月で初代の猫が亡くなり、しばらくしてやはり寂しくなり、2代目を飼い始めた。同じ猫といっても随分と性格が違うので新鮮である。前の猫は必ず、決まった時間につまり朝早く、私を起こす。寝ていると顔の周りをひげでこするので目が覚める。それでも起きないと次に障子をツメでひっかいて耳障りな音を出す。障子は丈夫なプラスチック製の紙なので破れることはないがさすがに我慢できなくて起きてしまう。今の猫はまだ一歳の若い猫なので起こし方は遠慮がちである。やはり、猫の気配を感じて目を覚ますがその時は猫が近くに居るという風である。朝ゆっくりと寝ることはできないので、十分な睡眠をとろうとすると早く寝るに限る。猫は家族の一部になっているのでもっとも手間がかかる。
ほかに水槽にカワムツを5,6匹入れている。これは奈良の川で採れたものを引き取ってきたがまだ生きている。できれば水槽ではなく、もっと広い池に放して繁殖させたいが、まだ池の構想がかたまっていない。できれば近くの水路の一部にでも放流できればと考えている。
昨年の海水浴に志度湾に行ったときに海辺にいた赤いカニを捕まえて飼っていたが、結局長生きしなかった。陸カニのようでもあり、適切な生息環境を整えられなかった。海の生物は余り慣れていないせいか大抵失敗する。
実は野鳥に興味があって、千葉に住んでいるときは近くに藪や林がたくさんあり、いつも鳥の鳴き声に囲まれていた。うぐいす、メジロ、コガラなど庭木に来ることもあった。しかし、高松には田畑が多い反面、雑木林や藪などは場所が限られており、近くにない環境のせいか、鳥の種類がすくないような気がする。それでも、ひばり、カラス、トビはいつも近くにいて、よく目にする。
シンガポールに2年ほど住んでいたが、住人のほとんどは中華系であり、年寄が籠に入れた鳥の鳴き声を楽しむという昔からの風習があり、町を歩いていると鳥かごを見かけて懐かしく子供時代を思い出した。今は野鳥を飼育することは許されていないが、子供の頃の楽しみのひとつは冬になると餌がとぼしくなり、野鳥を捕獲してうまく餌付けすることができたら、飼って鳴き声をたのしむことができた。今ではそれはできないので、野外観察で楽しむ程度である。田を耕すと虫が土から飛び出してくるので、トラクタの後ろにはカラス、セキレイ、ほかに名の知らない小鳥が狙って集まってくる。時期によってはシラサギが十数羽もきたのには驚いた。
魚にしろ、鳥にしろ、飼育するにはそれなりの環境を作らなければならない。そして、それを維持するのはさらに難しい。それよりも今では自然のままの姿を見て楽しむのが本来の姿を見られて楽しいと思う。だから、鳥や魚、虫などの生息環境を守り、維持していきたいと思うのである。無農薬栽培を行うのも、虫や貝、魚、鳥などが昔ながらに生きていけるための環境を作るためである。

トラクタについて回るサギの群れ 
カワムツの水槽