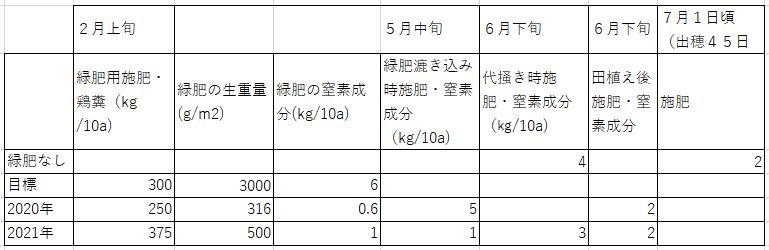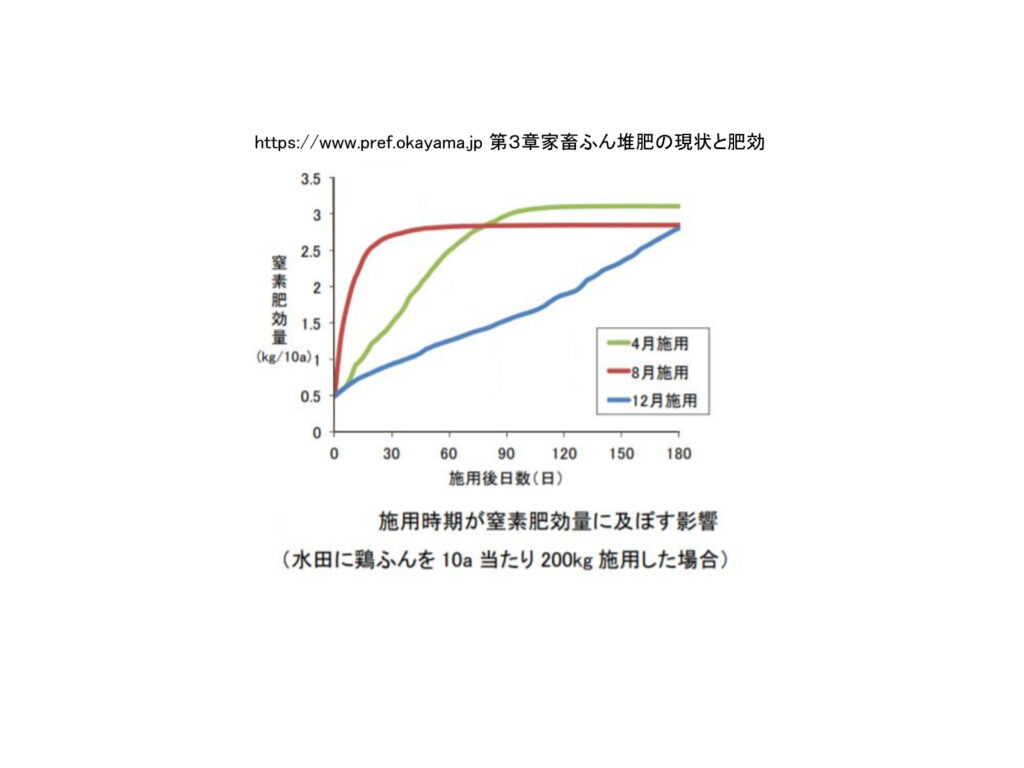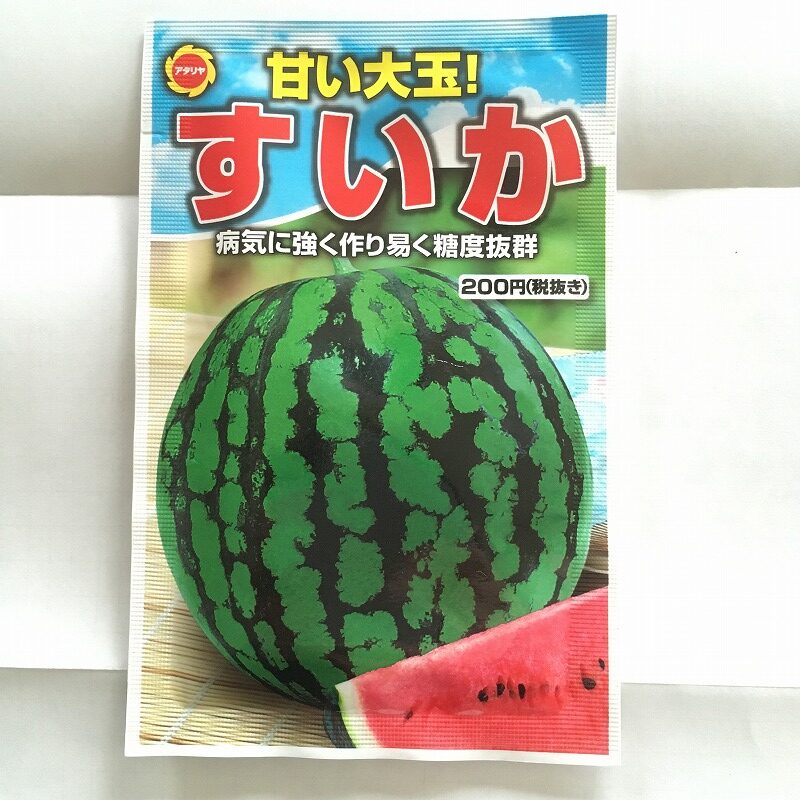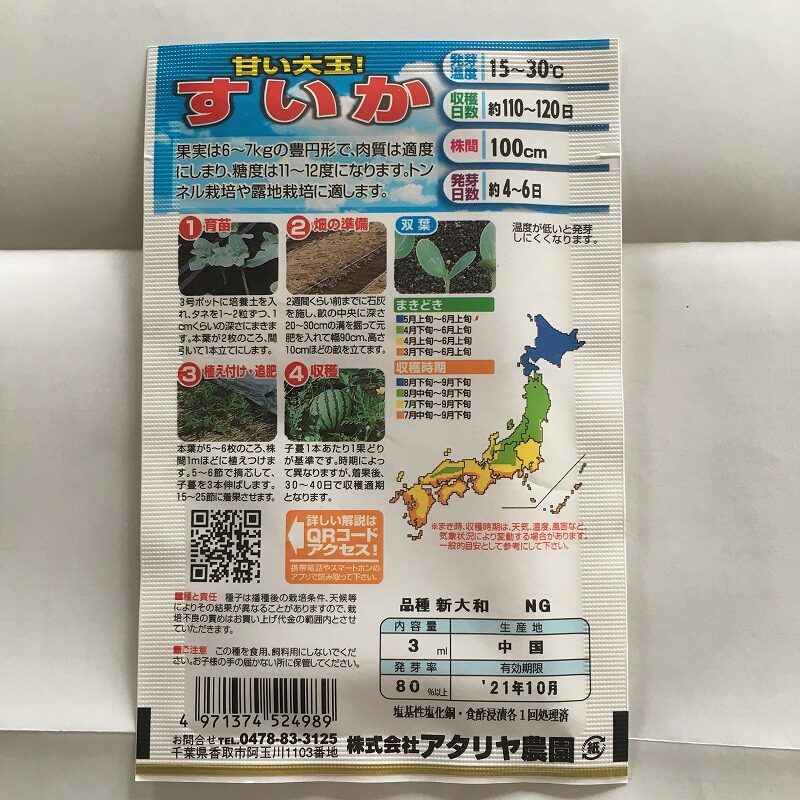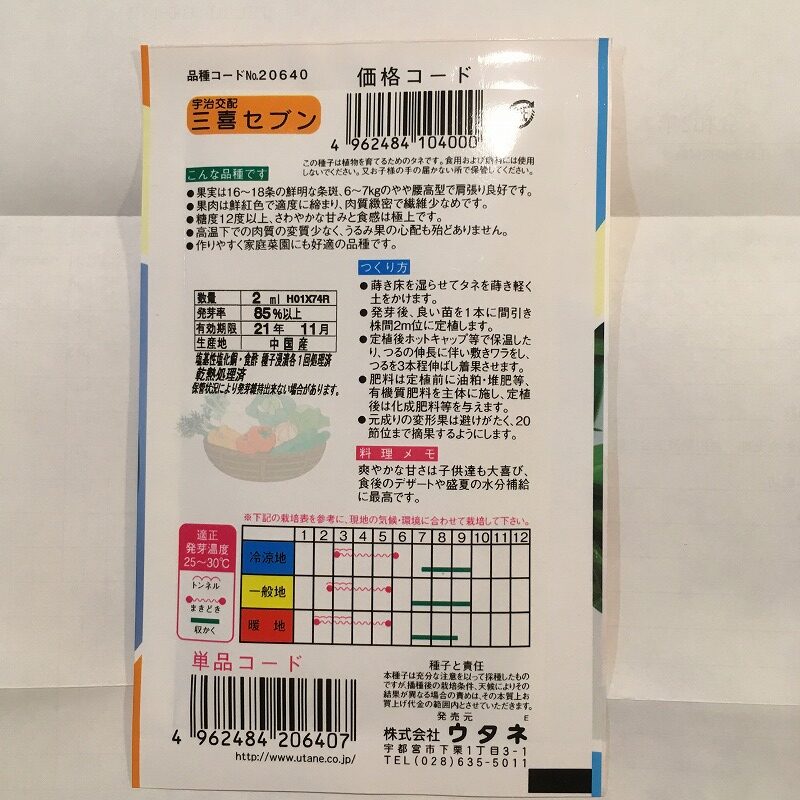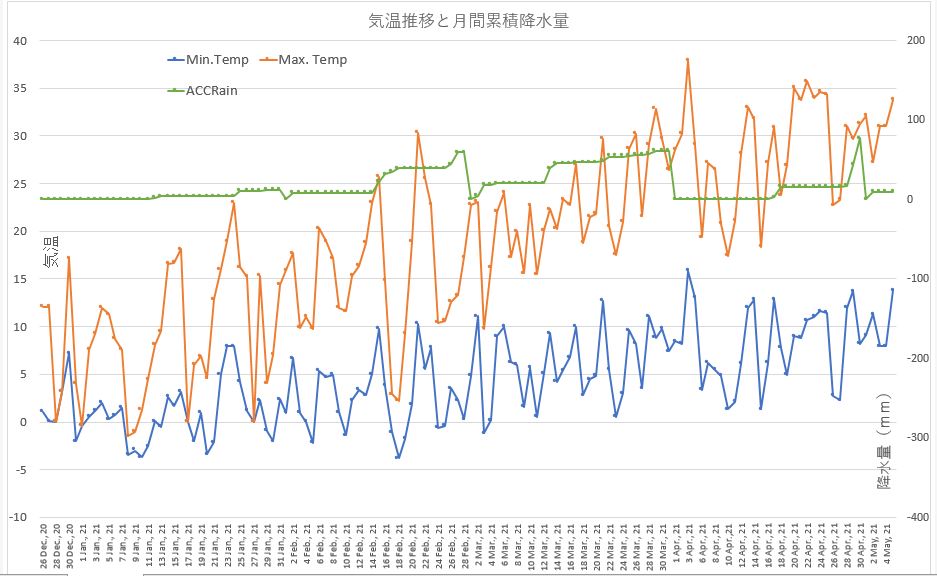田植えから逆算して35日前の今日5月15日に種もみの播種を行う。種籾は浸種後、2日間冷蔵庫で5℃で保存した後、前日に取り出し、乾燥しておいた。十分発酵させた土ボカシをふるいに掛け、必要な15kg程度を選別しておいた。幅1mの短冊の1.5m長さ区画に種もみ1合と土ボカシ750gを均一に播く。そこで、予め、籾1合を小分けしてビニル袋に入れる。そして土ボカシも750gを袋に入れて、必要な数だけ小分けしておく。そして、東側の短冊9.5mに対して「ニコマル」を播き、中央の短冊9.5mに対して「コシヒカリ」を播く。コシヒカリは山形産を南側に香川産を北側に播いている。3本目の短冊は5.5mで「クレナイモチ」を播種した。種籾と土ボカシを播いた後、もみ殻燻炭をフルイに掛けながら種もみが見えないように被覆する。そして、最後に厚板を使い、籾を土に密着させるために鎮圧を行う。ここまでで午前中いっぱいの仕事量である。籾殻燻炭の被覆を2短冊分、手伝ってもらった。午後はカンレイシャのトンネルを張る。1m幅に紐を張っており、この少し外側に包丁で紐に沿って切れ込みを入れる。この切れ込みにカンレイシャの裾を押し込む。トンネルの支柱を50㎝毎に2人で差し込む。次に10m長、幅2.1mのカンレイシャを支柱に被せ、長さを確認した。カンレイシャが縮んでおり、9.5m長に足りず、8.5mくらいの長さになり、端を差し込んだ。カンレイシャのトンネルは主に風やウンカなどの防虫対策として設けた。今日は午後から雨の予報であったが、トンネル張りを終了するころ(午後3時半)に雨が降り出した。今日は四国地方も梅雨入りしたそうで、例年より3週間早いという。午前中は日が出てかなり暑かったが午後は曇り、湿度は高いが温度はそれほどでもないので作業ははかどった。明日は筋肉痛で動けないかもしれない。

前日の種籾乾燥 
前日の短冊水抜き 
土ボカシの計量と小分け 
1.5m分の土ボカシを袋に小分け 
種籾と土ボカシを播いた 
種籾播種後 
もみ殻燻炭で被覆。 
3つの短冊が鎮圧まで終了 
トンネル支柱設置 
カンレイシャトンネル設置後