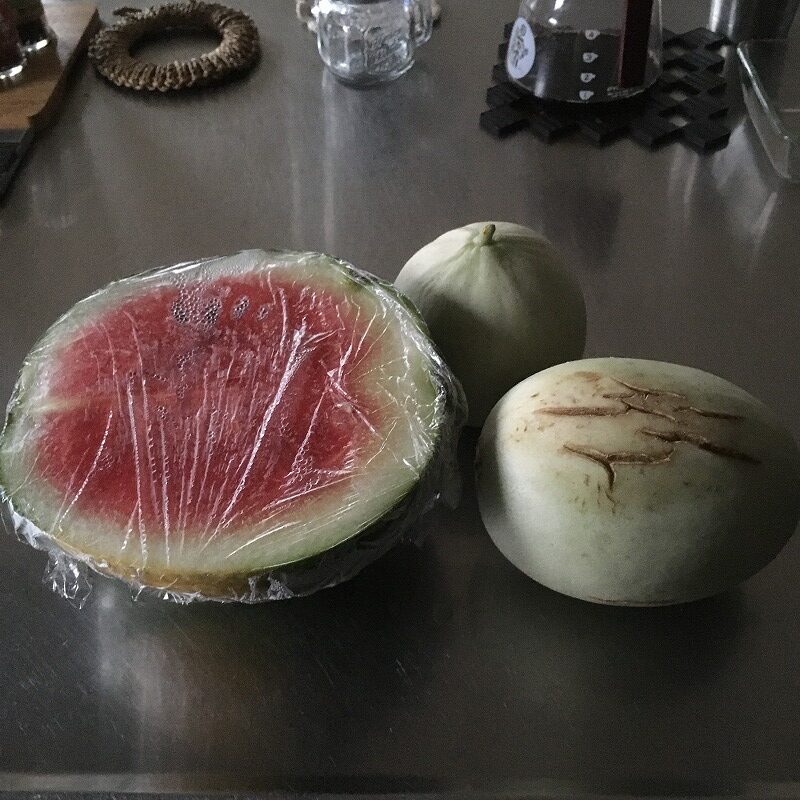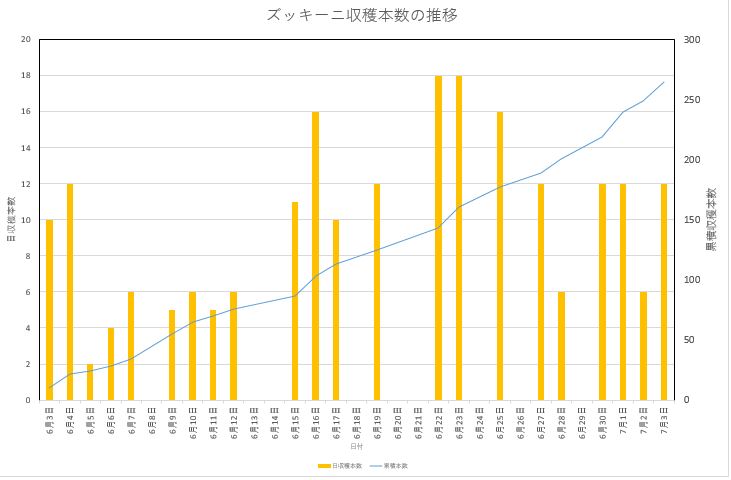6月20日に田植えし、3週間が経過した7月11日に2回目のコロガシ除草(横方向)を行う。出穂は8月16日なので7月11日は出穂前37日目となる。初期を抑えて寂しく作り、出穂前40-45日頃に本格的追肥を行うというのが「への字」稲作である。そこで少し遅いかもしれないが、コシヒカリのみ、反当り窒素成分2㎏相当の追肥を行う。具体的には醗酵鶏糞45㎏を水田No.5(5アール)に施肥する。田植え後に抑草のために米ぬか3袋をNo.5に散布している。これは窒素成分で1.2㎏に相当する。これは元肥になるかもしれないが、6月30日までに水入れの際に散布している。田植え直前の6月13日に元肥として醗酵鶏糞45㎏をNo.5に施肥し、耕耘している。そこで総計5.2㎏相当の窒素成分を与えている。これ以外に緑肥を田植え1月前に漉き込んでいるから、緑肥もゆっくりと窒素成分を供給する。イネの生涯に必要な肥料(窒素成分で反当り5㎏)を十分与えている計算になる。もし、これで過繁茂の草出来となり、イネが倒伏する時には元肥が多かったということになるだろう。あるいは、病気が出て、収量が少なくなれば、追肥が多すぎたということになる。

7月12日苗代跡クレナイモチ 
7月12日No.5コシヒカリ 
7月12日No.5コシヒカリ 
7月12日右端5列クレナイモチ 
7月12日No.4ニコマル 
7月12日No.5コシヒカリ