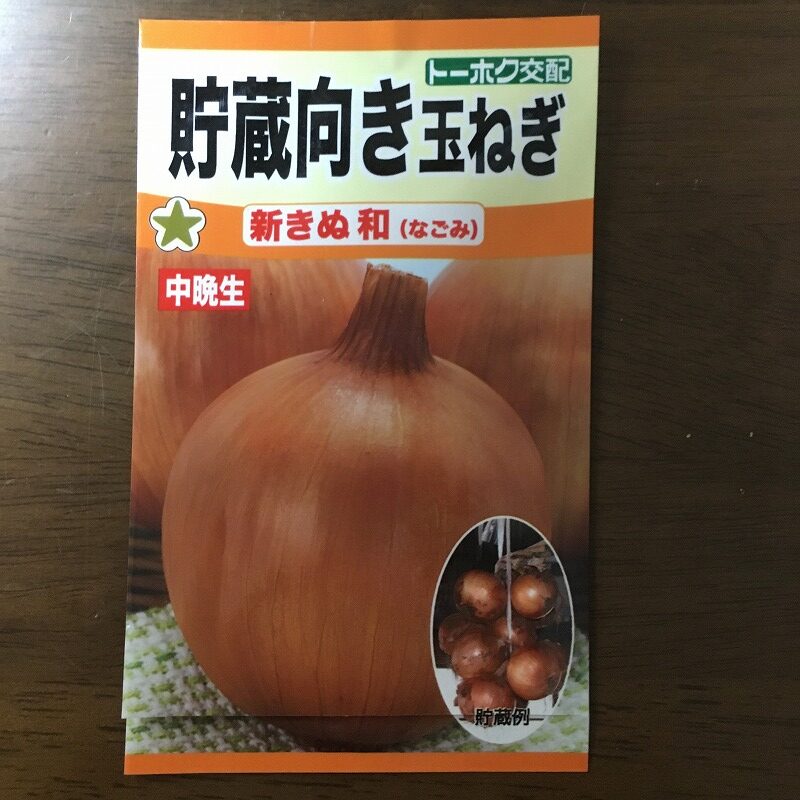今年はもち米を作って、58㎏の玄米が取れたので餅つきをする。精米はJAのコイン精米機で行うのだが、もち米に対応しているかどうか判然としない。しかし、精米の度合いを選択するボタンの中に「標準(もち)」とあり、いつもは「クリーン無洗米」を選ぶのであるが、標準を選択した。もち米は「クレナイモチ」という品種でこの地域では一般的な品種である。
餅つき機はもっていないので、妹夫婦に借りて、前日から4升(1升は1.8L、重量で焼く1.5㎏)のもち米を洗って水に浸けておく。香川は餡入りモチが郷土の味であり、モチに入れる餡はあらかじめ、購入して丸めておく。餅つき作業はつき上がってから固くなるまでの時間に餡を入れて閉じて丸める。経験者である妹夫婦のアドバイスに従い、準備をおこなっている。餅つきはもち米を蒸して、臼に移して、杵でつくのが正道であるが、餅つき機では十分、水を吸わせて、水切りをしたコメを餅つき機に入れるだけで、蒸して、つくことができる。道具立てが少なくて済む。
鏡もちや餡なしの白餅、餡入りモチを合わせて2升、エビ入りとノリ入りの切り餅(のしもち)をそれぞれ1升を4回のサイクルで餅つきを行った(12月28日)。出来上がったモチを適度の大きさに切り分ける「餅とり器」を使ったが便利である。出来上がったモチは熱くて、素手で切り取っていくのは手を焼けどするほどの熱作業である。出来上がったモチを容器といっしょに持ちとり器に移し替え、ハンドルでスクリューを回してモチを出口に強力に押し出す。適当な大きさで出口に設けられたカッターで切り離す。これであれば、手で直接、熱いモチに触れることはない。ただし、モチを移し替える際に捏ねる羽根を取り除くことが必要であり、埋もれてしまうと取り出すのに熱作業となるが、要領が判れば、羽根の取り出しはそれほどの熱作業とならない。 餡いりもちは切り取 ったモチを広げて、餡を入れ、閉じて、丸めるのであるが、モチが冷えると固くなって、モチを切り取るのがむつか しくなる。だから、一人では無理で、2人以上が必要である。妹夫婦と4人で教えてもらいながら3時間弱で終えることができた。エビやノリなどは蒸しあがったモチ米をつく工程に入る際に、上から、投げ込むだけである。つく工程で均一に混ざっていく。
いづれにしても、餅つきは共同作業で大勢でわいわい言いながら、つくのが楽しい。完全に機械化するとこの本来の楽しさがなくなってしまう。千葉に住んでいたころの自治会の最大のイベントは餅つき大会で、大勢が参加して、蒸す人、臼でモチをつく人、取り分ける人、雑煮を作る人、飲み物、のり、きなこ、餡、おろし大根などをパックにして、食べやすくする人などでその日は朝はやくから、自治会のほとんどの人が顔を出して、準備したり、食べに来たり、久しぶりの対面で話がはずみ、食べながら雑談し、交流する良い機会となり、盛り上がったものである。是非、今の自治会でもできればやりたいと考えている。(12月30日)

餅の切り分け器(分解洗浄) 
餅つき機(蒸して、捏ねる) 
出来上がった4升のモチ